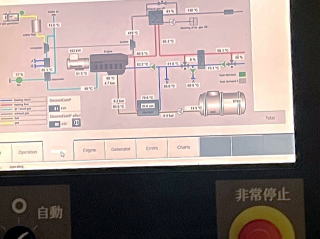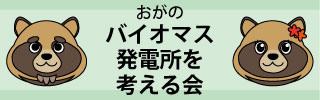
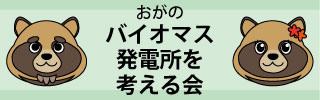
| 目次 | 1-1バイオマスって何!? | 1-2バイオマス発電の種類 |
| 1-3火力発電の仕組み | 1-4バイオマス燃料には何がある? | |
| 1-5木質バイオマス発電と森林の関係は? | 1-6木質バイオマス発電と林業の関係は? | |
| 1-8バイオマス発電はカーボンニュートラルか!? |

火力発電のしくみ(まとめ)
|
①燃料 |
②気体 |
③機械 |
④発電 |
|
天然ガス、石油、石炭、 |
蒸気 |
蒸気タービン |
発電機 |
|
天然ガス、石油 |
ガス |
ガスタービン又はガスエンジン |
|
|
石炭・バイオマスなど |
|
種類 |
燃料 |
主な用途 |
|
①木質バイオマス |
広葉樹・針葉樹 |
ボイラーの燃料、発電燃料など |
|
②バイオエタノール |
サトウキビ、トウモロコシ、木材など |
ガソリンの代替燃料 |
|
③バイオディーゼル |
植物性油脂をメタノールとの化学合成物 |
軽油の代替燃料 |
|
④バイオガス |
家畜の排せつ物、食品残さなどをメタン発酵させたもの |
発電燃料 |
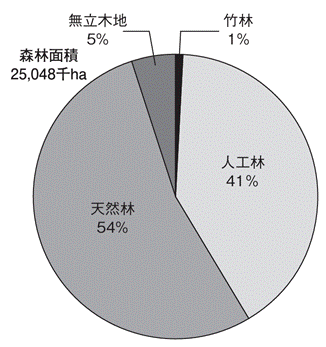

|
①植栽⇒②下刈り⇒③つる切り・除伐⇒④枝打ち⑤間伐 |
間伐と主伐の違い、林地残材との関係
|
伐採の種類 |
伐採目的 |
作業の種類 |
森林の状態 |
木齢(年目) |
材の利用状況 |
|
間伐 |
間引き |
切り捨て間伐 |
森林状態を維持する |
15~25 |
未利用 |
|
利用間伐 |
森林状態を維持する |
26~ |
・大部分は利用 (A・B材) ・一部は未利用 |
||
|
主伐 |
収穫 |
択伐 |
森林状態を維持する (状態としては利用間伐と同じ) |
||
|
皆伐 |
森林状態を維持しない(森林の更新) |

|
燃料の種類 |
電気の調達価格 (1kWhあたり) |
|
①間伐材等由来の木質バイオマス |
40円(2千kW未満) 32円(2千kW以上) |
|
②一般木質バイオマス |
24円(2万kW未満) 21円(2万kW以上) |
|
③建築資材廃棄物 |
13円 |
(出典:林野庁)
|
生育由来 |
間伐 |
主伐 |
|||
|
森林 |
民有林 |
その他 |
森林経営計画外 |
① |
② |
|
森林経営計画 |
① |
||||
|
保安林 |
|||||
|
国有林 |
保安林 |
||||
|
国有林野施業実施計画 |
|||||
|
国有林野施業実施計画外 |
② |
||||
(出典:林野庁をもとに作成)